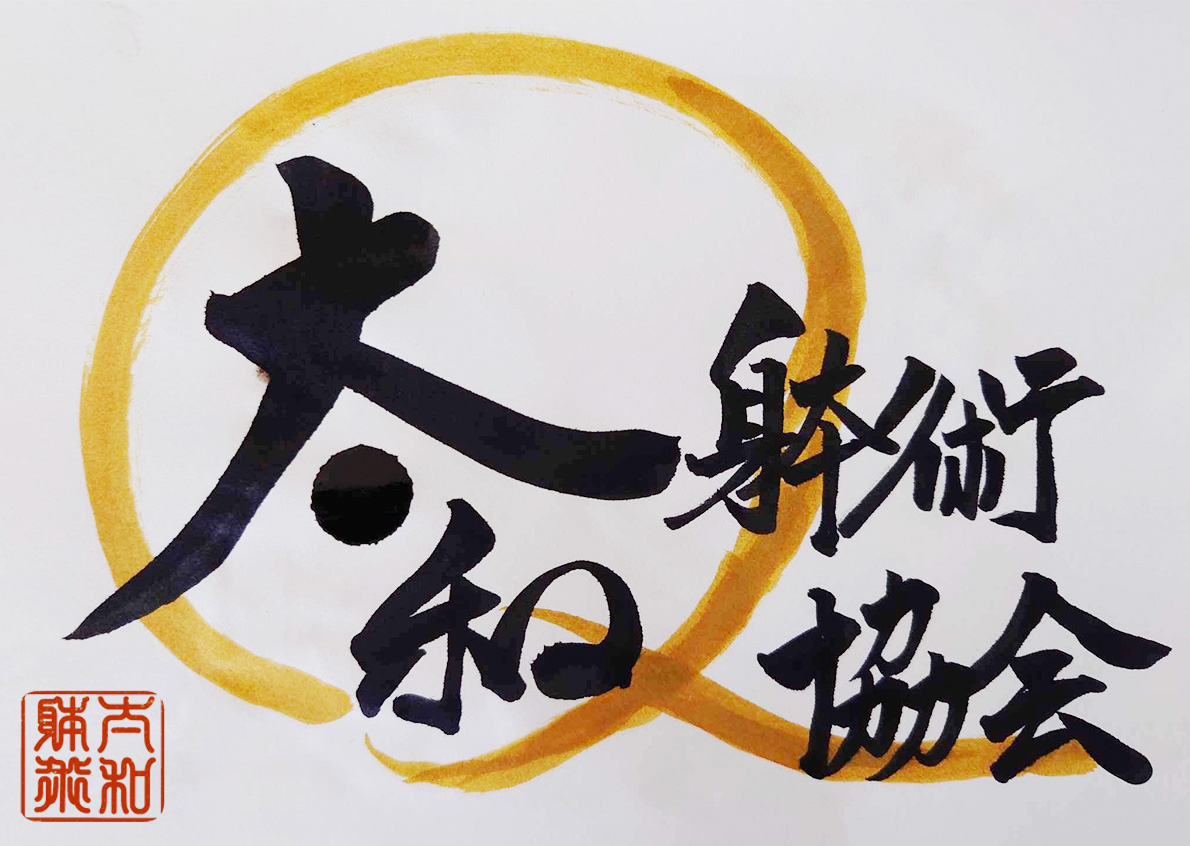2026年1月2日の午後、姜氏門二代伝人鄒淑嫻が中国重慶にて仙去いたしました。享年102歳でした。
以下、姜氏門公式サイト(中国)に掲載された当会代表伊与久大吾による弔辞の日本語訳を転載します。
ーーーーー
追悼 敬愛の恩師・鄒淑嫻を偲ぶ
いつかこの時が来るのは、頭では分かっていた。しかし、実際この日を迎えてみれば、頭の中は真っ白になり、手足は震え、何をして良いかも分からない体たらくだ。師父がこの私の様子を見たなら「男子漢、大丈夫だろ!」と、笑いながら叱咤激励されることだろう。
私が初めて師父の下を訪ねたのが、三十年前、確か1996年だったと思う。四川省に武術の研究に行った帰り、上海に武林の隠士が居ると聞いて、故・梁佃香師姐に連れられ早朝の魯迅公園に赴いた。
八卦掌の達人……と聞いていたのだが、実際現れたのが小柄な品の良い御婦人だったので、私は大層驚いたのを覚えている。御婦人はにこやかに私に語られた。
「お前は套路を学びたいのか? それとも本質を学びたいのか?」
私は咄嗟に「私は八卦掌の本質を学びたくて参りました」と答えていた。彼女は私の顔をじっと見て、少し考えるようにすると、「それならば、例え他の者が套路を練習している時でも、お前にはただ立ったり歩いたりしかさせないかも知れない。しかしそれはお前が望むものに至る最短距離なのだから、必ず耐えなくてはならない。これが出来るかな?」と尋ねられた。
私は吊られるように「はい、ご教授宜しくお願いします」と答えていた。この出会いが全ての始まりだった。
それから三年を経て、外国人としては例外的に拝師が許され、師父と弟子の間柄になった。以来、去年(2025年)私が重慶を訪れるまで、実に四半世紀以上もの間、師父は私の武術にただの一度も「可以」(よろしい)と言われることは無かった。
時には一年以上も師父の身辺で、まさに寝食を共にするように学び、私達の国にも三回来訪していただいた。私の訪中も数十回を数え、四十歳を越えるまでの私の生活の中心には、常に師父と姜氏門の武術が据えられていた。
厳しくも嬉しい練功の日々のエピソードは枚挙にいとまがないが、一つだけ紹介したい。
ある朝の修行の折、師父が脚を不思議な形にして動かされていた。曰くこれは「蹴り」の型である、と。まだ若かった私は、幼い頃に学んだ空手道の経験から「師父、そんな足形で相手を蹴っては、却って自分の脚を負傷してしまいますよ」と、余計なことを言ってしまった。すると師父は悪戯っ子のように笑い「果たしてそうかな?」と言うと、その変わった足形で私の構えた後脚を削り下ろすように蹴った。激痛とともに私はもんどり打って倒れ、暫くは片足を引きずって歩かざるを得なかった。
師父曰く、今の一技が「八卦腿(下八卦・八卦二路)」だとのことで、中国武術の奥深さとともに、普段はにこやかな師父を畏怖する心が否応なしに高まったのだった。
後に師父が「お前ほど叩いて教えた弟子は居なかった」と笑って語られたが、実際「いちいち叩くと手が痛くなる……」と言って、私を調教するための木の棒が用意されていた。それも今私の武館で「啓蒙の宝」として飾られている。
そんな私も母国へ帰り、所帯を持ち長男を授かった。初めて息子を連れて師父の下を訪ねたとき、師父は殊の外喜ばれ、「息子には厳しく、孫は甘やかす」と言って呵々大笑された。そして「お前はこれから私の徒児と名乗りなさい。」と語られたのだった。
師父が歳を重ねて行くにつれて、私も壮年になり、なかなか昔のように、その下を訪れることが出来なくなった。特にコロナ禍以降は、一年に一度も行けない年が続き、微信での会話も何処かしら寂しそうだった。
落葉帰根の故事に準じて、師父は生まれ故郷の重慶を終の棲家にするべく、長らく住み慣れた上海を後にした。その行動力と判断は、周りの人間を驚かせるに十分だった。今思えば、彼女の人生の最後の灯火が赤々と燃え上がった瞬間だったのだろう。
私を含めた古くからの弟子達は、皆その決定を心配していた……が、肉親や孫子、曾孫子輩に囲まれて、にこやかに笑う師父の姿を見て、それは安心に変わった。
2024年、師父百歳の冬、久しぶりに重慶の師父の下を訪れた。師父は少し小さくなっていたが、相変わらず日々の練功を続けられていたし、血色も良く、何より食欲が悪くなかった。
その日師父は、私に教える為に、前日から形意拳の「鶏形」を復習していたと言う。二日掛けて私に入念に教え、最後に私に「やって見せなさい」と言われた。
緊張しながらも、五行拳、鶏形……と演ずると、師父はポツリと「可以……不錯」(よろしい……悪くない)と言われた。
私は涙が溢れ出して仕方がなかった。
私が師父に学んだ教えは、つまるところ「生命の根源に遡る道」だったと思っている。その教えに生きて、その道を辿り、その通りに「生命の根源」へと旅だった師父。
今日、明日では、感謝や万感の想いは伝えきれないことは、私のなかでは明白なので、何時か私も貴女の居るところに帰着した時に、たっぷりと語り合いたいと思う。
師父、それまで仙境にいて私たちを見守っていてください。また必ずお会いすることを楽しみにしています。
徒児 伊与久誠博(大吾) 敬白